大吟醸とは、純米大吟醸とは?日本酒の「特定名称酒」を知ろう
2025.08.22
日本酒は、約2,000年もの歴史を持つ伝統的な日本の酒類で、全国に数多くの酒蔵が存在します。
売り場で目にする「隠岐誉」「高正宗」などの銘柄のほか、「吟醸」「大吟醸」といった名称が並びますが、初心者にとってはその違いが分かりづらいポイントです。
本記事では、日本酒の種類と選び方、味や香りの特徴について分かりやすく解説します。
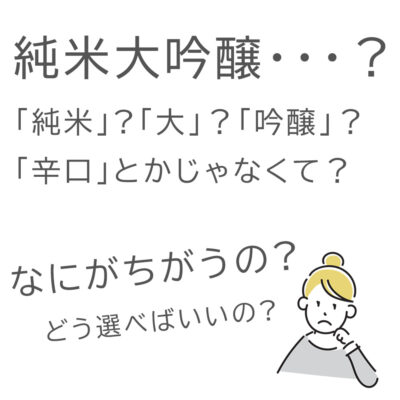
「どのように作られたお酒か」≒「特定名称」
ブランド(銘柄)の数もさることながら、日本酒はその材料や加工の仕方により、様々な種類に分別されます。
その「原材料」「作り方」がある条件に合致するものが「特定名称酒」、合致しない一般的なお酒が「普通酒」と大別されます。
さらに「特定名称酒」の中でも、合致する条件で枝分かれし、それが「純米酒」「吟醸酒」などと呼ばれるようになります。
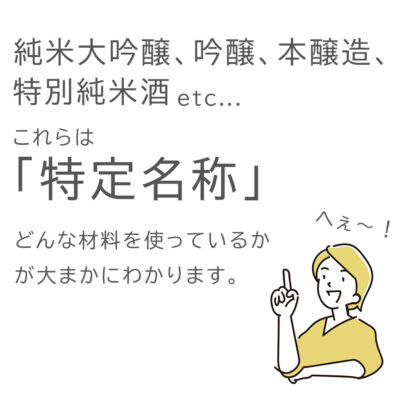
純米と書いてあれば純米酒、そうでなければアルコール添加酒
お米を原料に作られていることが広く知られている日本酒。実はそれぞれの原材料を見比べればお分かりいただけますが、大きく2つに分かれています。
日本酒のうち、原材料が「米・米麹・水」のものを純米酒、「米・米麹・水」に「醸造アルコール」を添加して作られているものをアルコール添加酒と呼びます。
醸造アルコールの役割は後述しますが、次にラベルなどでよく見る「吟醸」などの表記について説明します。
吟醸、大吟醸とは?
日本酒造りの工程は「精米」から始まりますが、どれだけお米の中心に近いところまで磨く(削り取る)かの程度は「精米歩合(=白米重量/玄米重量×100(%))」で表されます。
この精米歩合が70%以下のものを「本醸造酒」、60%以下のものを「吟醸酒」※、同じく50%以下の精米歩合のお米で作られているお酒を「大吟醸酒」と呼び分けます。
親しみのない数字なので少しややこしいですが、精米歩合は数字が小さいほど中心に近いところまで磨いている、と覚えてみてください。
※特別純米酒や特別本醸造酒といった区分のお酒も60%以下または特別な製造方法となっていますがここでは触れておりません。
純米酒かどうかと、どれだけ磨いたお米を使っているかで分かれている
原材料に醸造アルコールが添加されているかどうかと、どれくらい精米しているかで
「純米酒」「純米吟醸酒」「純米大吟醸酒」「本醸造酒」「吟醸酒」「大吟醸酒」といった呼び分け方になります。
他にも醸し方が特別である「特別○○」といった特定名称、さらに「生酒」「斗瓶囲い」「生酛(づくり)」というように、火入れのタイミング、搾り方、絞る前の加工方法の違いなどで色々と枝分かれしますが、大まかには純米酒かどうかで味の傾向が分かれると思っていただいて差し支えないでしょう。
醸造アルコールとは?なぜ添加するの?
「本醸造酒」「吟醸酒」「大吟醸酒」などに添加されている醸造アルコールですが、醸造アルコールそれ自体が何なのか、また添加されている目的はあまり知られていないのではないでしょうか。
この醸造アルコールは、サトウキビを原料とすることが多い、ほとんど味や香りのない、ほぼ純度100%のアルコールです。
原則、その10%までの重量を添加することが認められていますが、その目的は主に「香り成分をお酒に残すこと」にあります。
純米酒にももちろん香り成分は残っていますが、お酒を搾る際に酒粕の方に残りやすい香り成分が、アルコールを添加することでより液体(お酒)の方に移りやすくなるというわけです。
その点で、吟醸酒は純米酒に比べて特有の香りや風味が出やすくなっています。
味や香りはどう違うの?
では、例えば純米大吟醸酒と大吟醸酒で味や香りはどう違うのでしょうか?
同じお米とお水、そして麹や酵母、搾り方であれば、純米酒の方がお米の甘みを感じやすかったり、喉越しがすっきりとやわらかい傾向にあります。
本醸造酒に添加されている醸造アルコール特有の香りや、アルコール度数の高さなどで日本酒に苦手なイメージをお持ちの方は、是非「純米酒」をお試しください。呑み方に関しても、ロックで召し上がったり、冷たいお水や炭酸水などで割っていただくのも実はとても美味しいですよ。
「辛口」や「甘口」とはどう関係するの?
ここまで、特定名称の区分による日本酒の違いをご説明しました。
辛口や甘口といった味の違いについては、特定名称によって、例えば純米酒だから甘口、本醸造酒だから辛口といった違いにはなりません。
ラベルや商品ページに記載されている「酸度」や「日本酒度」で大体の分類がされていますが、また別の記事で詳しくご説明をさせていただきます。












